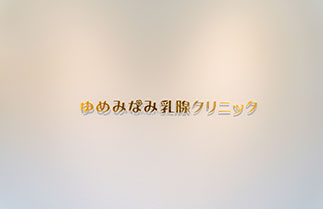日本人の乳がん
日本では、1年間に乳がんと診断される女性が約10万人にのぼり(2019年は97,142人)、生涯で9人に1人の女性が乳がんになる可能性があります。乳がんになる年齢には2つのピークがあり、1つ目は45~50歳、2つ目は65~70歳です(図1)。最近では、生活環境の変化や平均寿命の延びにより、乳がんを発症する年齢が高くなる傾向があります。県立広島病院でも、最近5年間では70~79歳の患者さんが最も多く、昨年は80歳以上の方の乳がんが増えてきています(図2)。
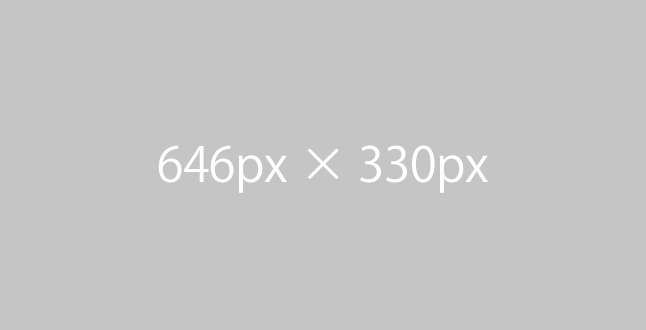
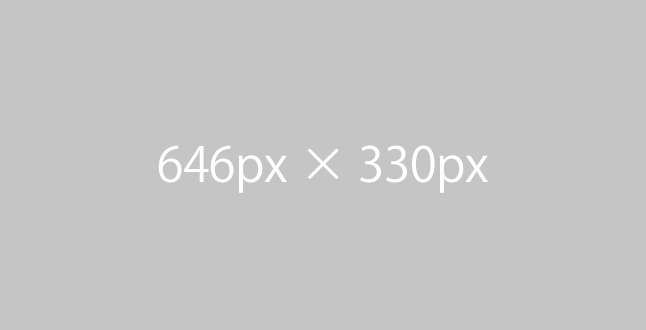
一方で、乳がんの治療成績は年々向上しています。特に、手術とあわせて行う薬物療法の進歩が影響していると考えられます。乳がんの進行度(病期)ごとの5年間の生存率を見ると、
0期(最も早期の段階):100%
Ⅰ期:98.9%
Ⅱ期:94.6%
Ⅲ期:80.6%
Ⅳ期(遠隔転移がある状態):39.8%
このように、乳がんは早期発見・早期治療をすれば高い確率で長く生きられる病気になっています。ただし、がんが転移してしまうと(Ⅳ期)、5年後の生存率は40%を下回ります。そのため、乳がんの早期発見や、再発を防ぐ治療がとても重要です。
(参考にした情報)
国立がん研究センター:がん統計 最新がん統計
https : //ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html 2022年10月5日参照
乳がん検診
日本では、乳がん検診を受ける人の割合が全国平均で約36~37%と低く、広島県ではさらに低い32~35%となっています。これは、アメリカ(70%以上)やイギリスと比べると大きな差があります。
なぜ欧米の受診率が高いの?
アメリカ:検診が保険でカバーされており、医療費が高いため「病気になる前に検診を受ける」習慣が根付いている。
イギリス:国の制度として対象者をリスト化し、定期的に検診を受けるよう勧める仕組みがある。
一方、日本の乳がん検診には「住民健診」(市区町村が行うもの)と「人間ドックなどの任意検診」(企業や個人が受けるもの)の2種類がありますが、どちらの受診率も低いのが現状です。
このため、日本全体で乳がん検診を受ける人を増やす対策が必要とされています。
乳がん検診を受けない理由は?
調査によると、日本の女性が検診を受けない理由には、次のようなものがあります。
したがって検診の受診率を上げるには、
- 正しい知識を広め、検診の重要性を知ってもらうこと
- 痛みや不安を軽減できる方法を紹介すること
- アジア人の乳房の特徴に合った超音波検査を選択しとして増やすこと
が必要です。
乳がんは早期発見・早期治療で90%以上が治る病気です。
定期的に検診を受けることで、健康を守ることができます。
自分のため、そして大切な家族のために、ぜひ乳がん検診を受けることを考えてみてください。
フォックス岡本聡子:これからの乳がん検診はこうなる!肌で感じる,日本とアメリカの乳がん検診事情の違い. Rad Fan 2023; 21(12): 37-41.
乳がんのセルフチェック
乳がんのセルフチェックは、早期発見のために重要な習慣です。セルフチェックを定期的に行うことで、乳房の変化に気づきやすくなり、異常があれば早めに医療機関を受診することができます。
セルフチェックのタイミング
以下のwebサイトで、セルフチェックの方法と注意点を学べます。
https://www.ganclass.jp/kind/breast/selfcheck
乳がん治療
乳がんの治療方法は、がんの進行度(病期)やタイプ、患者さんの年齢や体の状態に応じて選ばれます。
以下のwebサイトで乳がんの進行度(病期)や治療について学べます.
https://ganjoho.jp/public/cancer/breast/treatment.html
乳がんの主な治療方法は以下のとおりです。
① 手術(外科的治療)
乳がんの基本的な治療で、がんのある部分や乳房全体を取り除く手術です。
‐乳房部分切除術(温存手術):がんがある部分だけを切除し、できるだけ乳房を残す手術。多くの場合、放射線治療と組み合わせます。
‐乳房全摘術:乳房全体を切除する手術。必要に応じて、乳房再建手術を行うこともできます。
‐センチネルリンパ節生検:センチネルリンパ節とは、がんが最初に転移する可能性が高いリンパ節のことです。手術中に、特殊な色素や放射性物質を使ってセンチネルリンパ節を特定し、そのリンパ節だけを切除して、がん細胞の有無を調べる手術方法をセンチネルリンパ節生検といいます.
‐腋窩リンパ節郭清:脇の下(腋窩)にある複数のリンパ節を広範囲に取り除く手術です。
すでにリンパ節転移が確認されている場合やセンチネルリンパ節にがん細胞が見つかった場合(特に転移が大きい場合や複数ある場合)に行われます.
②放射線治療
手術後に、残っている可能性のあるがん細胞を破壊するために行います。特に乳房部分切除術後には、再発を防ぐ目的で多くの患者さんがこの治療を受けられます.
③ 薬物療法(全身治療)
乳がんは目に見えないレベルで体の他の部分に広がっている可能性があるため、薬による治療が行われます。
‐ホルモン療法:エストロゲン(女性ホルモン)によって成長するタイプの乳がんに対して、ホルモンの働きを抑える薬を使います。
‐化学療法(抗がん剤治療):がん細胞の増殖を抑える薬を使用。進行がんや再発リスクが高い場合に用いられます。
‐分子標的治療:特定のがん細胞だけを狙って攻撃する薬。代表的のものとして,HER2陽性乳がん(HER2というタンパク質が多いタイプ)に有効な抗HER2薬がこれにあたります.
‐免疫療法:がんに対する体の免疫を活性化させる薬(免疫チェックポイント阻害薬)を用いた治療法。一部の乳がん(トリプルネガティブタイプなど)で適用されます。
早期乳がんの治療:
早期乳がん(0期~ⅢA期)は、転移がない、またはリンパ節転移が限られている状態の乳がんです。この段階では、がんを根治できる可能性が高く、適切な治療を受けることで長期的な生存が期待できます。
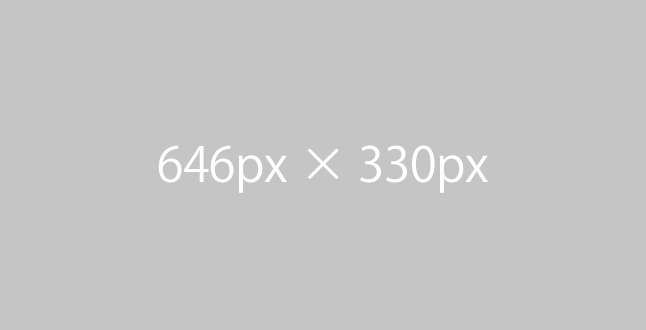
- 非浸潤性乳管癌(腫瘤性病変,石灰化病変-1, 2)
- 浸潤性乳管癌(1, 2)
- 浸潤性小葉癌(1, 2)
- 男性乳癌
局所進行乳がんの治療(ⅢB,ⅢC期):
乳房内や周囲のリンパ節に広がっている状態の乳がんですが、遠隔転移はない状態です。治療は、化学療法(抗がん剤) を先行し、腫瘍を小さくしてから手術 を行うことが一般的です。必要に応じて放射線治療 や ホルモン療法・分子標的治療 を追加し、再発を防ぎます。
再発・転移乳がん(Ⅳ期)の治療:
乳がんが再発したり、他の臓器に転移している状態であり、手術ではなく薬物療法を中心に治療が行われます。患者さんの病状に応じて、化学療法、ホルモン療法、分子標的治療,免疫療法などを組み合わせます。完治が難しい場合が多いですが、治療を続けることで長期間のコントロールが可能になっています。
※乳がんの治療は,個々の患者さんの乳がんの性質(ホルモン受容体、HER2発現、遺伝子変異など)を考慮して、最適な治療法を選択する「個別化治療」あるいは個別化治療に患者さん一人ひとりの遺伝子情報や体質、生活習慣、価値観などを組み入れた「オーダーメイド治療」が行われます。
がんの種類や進行度によって最適な治療法が異なるため、専門医と相談しながら治療方針を決めることが重要です(図3,4)。
乳がん手術後のフォローアップ
乳がんの手術を終えた後も、再発の早期発見や治療の合併症の管理、生活の質の維持 のために定期的なフォローアップが大切です。
フォローアップの目的としては以下の項目が挙げられます
・再発や転移の早期発見
・手術後の合併症(リンパ浮腫など)のチェック
・ホルモン療法や化学療法などの副作用管理
・生活習慣や健康管理のサポート
フォローアップの頻度と内容については,当院ホームページ内の診療案内・乳がん術後外来(保険診療)をご参照下さい.
注意すべき症状と受診のタイミング
乳がんの再発や転移の可能性があるため、以下のような症状があればすぐに受診してください。
‐局所再発のサイン
・乳房や手術跡のしこり、違和感
・乳房のくぼみや皮膚の変化
‐遠隔転移の可能性がある症状
・骨の痛み(転移の可能性)
・長引く咳や息切れ(肺転移の可能性)
・食欲不振・体重減少・黄疸(肝転移の可能性)
・頭痛・めまい・手足のしびれ(脳転移の可能性)
術後の生活で気をつけること
・バランスの良い食事(栄養をしっかり摂る)
・適度な運動(ウォーキングなど無理のない範囲で)
・禁煙、節酒(再発リスクを下げる)
・十分な休養とストレス管理(ホルモンバランスを整える)
以上の点に注意しながら手術後のフォローアップを受けていただきます.
乳がん手術後の自己検診
乳房のセルフチェックは、手術後も引き続き重要です。手術を受けた部分、温存した乳房、そして手術をしていない側の乳房(対側乳房)を、毎月1回、決まった日に丁寧に確認しましょう。局所再発や対側乳房の乳がん発見のきっかけになることがあります.
特に、片方の乳房に乳がんを発症した場合、対側の乳房にも乳がんが発生しやすい傾向があります。そのため、セルフチェックを習慣化し、少しでも気になる変化があれば、早めに受診して主治医に相談することが大切です。
【乳がん術後の局所再発の発見のきっかけ】
・手術した側の乳房の皮膚が赤くなる
・皮下にしこりを感じる
・乳頭からの異常分泌
・腋窩のリンパ節が腫れるはれる
【対側乳房の乳がん発見のきっかけ】
・しこり、ひきつれや痛み,乳頭異常分泌などの自覚症状
定期的なセルフチェックと医療機関での検査を併用し、安心して過ごせるようにしましょう。
乳がんセカンドオピニオンについて
乳がんと診断されたとき、多くの方が「この治療法で本当に大丈夫なのか」「他に選択肢はないのか」と不安に感じることがあります。そんなときに役立つのが セカンドオピニオン です。
セカンドオピニオンとは?
セカンドオピニオンとは、現在受けている診断や治療方針について、別の医師に意見を聞くことを指します。現在の担当医とは異なる視点から診断や治療法についてアドバイスを受けることで、より納得のいく治療を選ぶことができます。
当院でもセカンドオピニオンを予約制で受け付けていますので,お電話での予約をお願いします.また、病状を正確に把握し、十分な検討を行うために、セカンドオピニオン外来の予約日より前に、担当医の先生からの紹介状と検査結果の資料(病理診断、画像診断、画像データ、血液検査データなど)をご持参いただくか、ご郵送いただく必要があります。また,ご家族からのご相談の場合は、ご本人との関係が証明できるものをご持参下さい.
遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)について
乳がんを発症された方で、若年で発症されたり、血縁者(第3親等内)に乳がんや卵巣がんを発症された方がいる場合にはHBOCの可能性があるため,保険診療内で遺伝子の検査(遺伝学的検査)を受けることが出来ます.当院からHBOC総合診療基幹施設に紹介させて頂きますので,該当する方はご相談下さい.
HBOCの特徴や遺伝子検査について説明させていただきます。
HBOCの特徴について:
HBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)は、BRCA1 や BRCA2 という遺伝子に変異があることで、乳がんや卵巣がんの発症リスクが高まる遺伝性の病態です。特に40歳未満での発症や、家族内で乳がんや卵巣がんの患者が多い場合に、HBOCの可能性が考えられます。男性でも乳がんや前立腺がんのリスクが高まることが知られています。
HBOCのリスクがある場合、遺伝子検査 によって確認でき、早期に適切な対策を取ることが重要です。定期的な検診に加え、予防的手術を検討することもあります。
HBOCの遺伝子検査について:
2020年の診療報酬改定により、以下のいずれかの条件に当てはまる場合、保険適用(3割負担で約6万円)でBRCA1/2遺伝子検査を受けることができます。
- 乳がんと診断された方
・45歳以下で乳がんを発症した場合
・60歳以下でトリプルネガティブ乳がん(ホルモン受容体・HER2が陰性の乳がん)と診断された場合
・2つ以上の乳がんを発症した場合(多発乳がん)
・家族(祖父母・両親・兄弟姉妹・子ども・叔父叔母・いとこなど)に乳がん・卵巣がん・膵臓がんの患者がいる場合
・男性の乳がん患者
・血縁者にBRCA1/2遺伝子に病的バリアントがある場合 - 乳がんと診断されていない方
・卵巣がん・卵管がん・腹膜がんのいずれかを発症した場合
HBOCと診断された場合の対応:
BRCA1/2遺伝子に病的バリアントがあると分かった場合、以下の対応が保険適用になります。
・乳房切除術(予防的乳房切除)
・卵管、卵巣摘出術(予防的卵管卵巣摘出)
今後の課題と展望
HBOCに関する医療は進歩していますが、まだ十分に対応しきれていない点もあります。
(参考文献)
平沢晃:HBOCの最近の話題,HBOC診療にかかる保険診療上の課題.第64回日本婦人科腫瘍学会学術講演会記録.2023; 41(2):207-209.